今の流行りは寿司ですよ 『希望のかなた』アキ・カウリスマキ
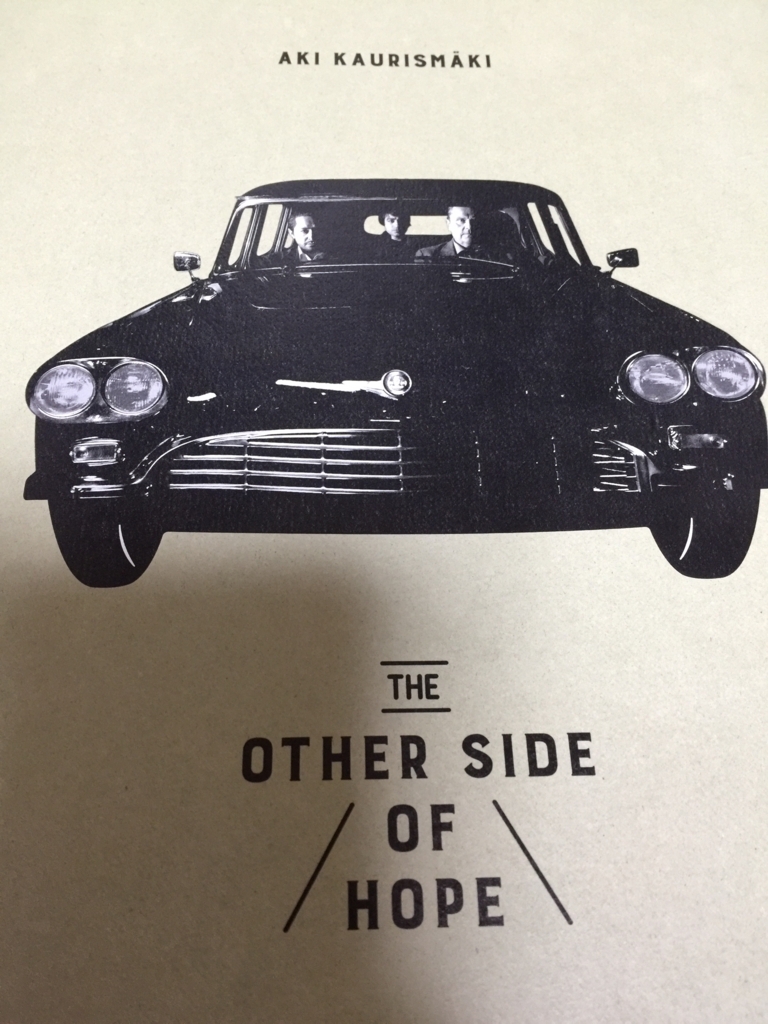
アキ・カウリスマキの最新作であり、前作『ル・アーブルの靴磨き』から続く「難民三部作」(元は「港町三部作」と呼ばれていたが、いきなり変更された)の二作目である。
今作でもカウリスマキのトレードマーク(犬、音楽で心情を表現する演出、シンプルなカメラワーク、あざやかな色彩、極端に少ないセリフ、個性的な顔の俳優たち)は健在である。しかし、いつも通りのカウリスマキのようで、新しい部分もある。
それはシリアからフィンランドに密航したシュルワン・ハジが亡命を求め、移民申請のための取り調べを受けるシーン。取調官の前で、ハジは移民となった経緯を淡々と話す。政府軍の空爆で家族が殺され、唯一生き残った妹と命がけの逃亡、その妹ともはぐれ、最後の希望がフィンランドへの亡命であること。自分の望みは妹を探し出し、フィンランドに呼び寄せること。ただそれだけだと。
家族を殺されたことを、ハジは必要以上の感情を交えず、淡々と話す。その顔をアップでカウリスマキは撮り続ける。寡黙を良しとするカウリスマキの映画で、ハジは長いセリフで自分たちの危機と、難民の現実について語り続ける。
カウリスマキのミニマムな世界観において、このシーンには異質なものを感じる。このシーンには難民について作り手からの強いメッセージがある。
カウリスマキは本作について、難民についてのヨーロッパの偏見を打ち砕く「傾向映画」として作ったと語っている。そのためにいつもの寡黙さを捨てて、俳優の雄弁な語りによってリアルな難民の姿を表現しようとしている。
こういった志が、本作に「いつものカウリスマキ映画」以上の新鮮さを与えている。
また、本作の主人公、サカリ・クオスマネンも今までのカウリスマキの主人公たちとは一味違う。
酒浸りの妻と別れ、服の卸売からレストランのオーナーへの転職を夢見る無口な中年男。ここまではいつものカウリスマキの主人公だが、クオスマネンはレストランの開店資金を稼ぐために怪しげな賭場に乗り込み、大勝負を挑むのだ。
今までのカウリスマキ作品の主人公たちを思い出してほしい。マッティ・ペロンパーやマルック・ペルトラがこういうときに勝てたことがあっただろうか。カウリスマキの主人公たちはいつも敗者だ。特に金の絡んだ勝負には勝てない。ずる賢い奴らに金をむしりとられる、それが今までの主人公のパターンだったはずだ。
ところが今作のクオスマネンはしたたかに、順調に勝ち進み、なんとギャングの親玉から大金を巻き上げ、悠々と脱出することに成功してしまう。これにはおどろかされた。かつてカウリスマキの映画で、こんな大勝利があっただろうか?
立派な体躯にふてぶてしい顔のクオスマネン妙に頼もしい。このクオスマネンが購入したレストランの敷地に、移民収容所から逃げ出してきたハジが隠れ住む。
追い払おうとするクオスマネンにカッとなり、ハジはパンチを見舞う。すかさずクオスマネンが殴り返す。次のシーンではレストランでハジに食事がふるまわれている。
オーナーの「ここで働くか?」の提案に、ハジは力強く応える。こうしてハジはレストランの従業員として働くことになる。
フィンランドに逃げ延びたハジの前には、移民申請を機械的に否決し、強制送還を命令する冷徹な裁判所や、ネオナチかぶれの男たちによる暴力などが立ちふさがる。こういったヨーロッパの冷たい不寛容にどう立ち向かえば良いのだろう。カウリスマキの出した答えは人々の小さな親切の大切さである。
暴力にさらされながらも、ハジの周りはささやかな親切で満ちている。フィンランドへ向かう船の船員、収容所で出会う人たち、ホームレス、レストランのメンバー、そして「礼はいらん。素晴らしいものを運ばせてもらった」と言って謝礼を受け取ろうとしないトラック運転手。これらの人々の純粋な善意がハジへの救いとなる。
今作は難民をめぐる厳しい現実を描きながら、要所でユーモアがちりばめられ、映画の雰囲気をやわらかいものにしている。
自分が好きなのはレストランで働き始めたハジの期限切れビザをどうするか?というシーン。その解決方法があまりに都合が良すぎて、真面目なのかギャグシーンなのかよくわからない。
しかし、本作の笑いどころは満場一致で「寿司レストラン」のシーンだろう。これに至ってはいつもの「オフビートなユーモア」というより、もはやナンセンスギャグである。
売上の芳しくないレストランをどうしようと皆が頭を悩ませる中、「今の流行りは寿司だ」とウェイターのテキトーな提案で、レストランは一気に日本風につくりかえられる。
提灯で飾られた店内にドラが鳴り響き、法被とハチマキと前掛け(日本語で「最高級品 大勉強の店」と書かれているのがまたおかしい)を着けた店員が日本酒を運び、厨房では難しい顔をしたコックが寿司を握っている。シャリに刺身をのせ、さらにでかいスプーン一杯分のわさびをドンとのせた寿司のヴィジュアルはあまりに強烈だ。
デタラメな日本のイメージに頭がクラクラしてくる。これまでシリアスなシーンが多かった反動か、カウリスマキもここでは大いにボケ倒す。
だが、自分がもっともショックだったのはその前のシーン。寿司のつくり方を学ぶため、本屋で寿司の本を片っ端から購入する場面である。
クオスマネンは日本語で書かれた本を大人買いするが、なんとその中に池波正太郎の『真田太平記』と藤沢周平の『孤剣』の文庫本が含まれているではないか!
まさかフィンランドの、カウリスマキの映画でこの二冊が登場するとは思いもしなかった。カウリスマキはどこでこれらの本を知ったのか?もしや読んだことがあるのか?
こんな日本人にしか通じないギャグをさらっと入れてくることに、唖然とするやらおかしいやら、とにかくインパクトの強いシーンだった。
前作『ル・アーヴルの靴磨き』を、カウリスマキはあまりに都合の良いハッピーエンドで締めくくり、そして観客はそれを大いに祝福した。しかし今作のラストでは苦い結末が待っていた。
ハジは離れ離れになっていた妹を助けることに成功するが、非情な運命を辿ってしまう。現在のヨーロッパを取り巻く状況では、『ル・アーブル-』のようなハッピーエンドはそぐわないものになってしまったのかもしれない。
それでも、不思議と後味が悪くないのは、全てをやりきって座り込んだハジのもとに、寄り添ってくる一匹の犬のせいだろうか。
映画の終わりかたは唐突なように感じたが、あの後を映さないことがカウリスマキの優しさなのだろうか。その後、ハジがどうなったかを観客の自由な想像に任せられるように、見た人の頭の中で、ハジが幸福な結末を迎えられるように、あえてカウリスマキはあそこで幕を下ろしたのかもしれない。
順調につくられるなら、難民三部作は次が最終作となる。激しく移り行く世界の中で、次作はどのような結末を迎えるのか。
不安なのは今作の序盤で、カウリスマキ映画の象徴、カティ・オウティネンがフィンランドを去り、メキシコへと旅立ってしまったことである。
このカティ・オウティネンの不在がどこか不吉なものに感じられてならない。オウティネンが見切りをつけるほど、今のフィンランドは生きづらい場所なのかもしれない。
何年後かに最終作がつくられるとき、世界はどうなっているのだろうか。たとえ現実の世界がどれほど冷たく非情なものになっていたとしても、どうか『浮き雲』のときのような、幸福な結末でシリーズを締めくくってほしいのだが。
もっとも、シリーズ名がまた突然変わっているのかもしれないが‥‥‥。