チャットモンチーの思い出
チャットモンチーを初めて見たのはテレビのミュージックステーションだった。曲は『とび魚のバタフライ』で、幼い見た目や歌声から「中学生みたいなグループやなあ」と思った。そしてそのまま忘れてしまった。
次にチャットモンチーを見たのは数年後だ。寝付けない深夜、テレビのチャンネルを回し続け、チャットのライブ映像がたまたま目に止まった。
演奏されていたのは『親知らず』で、メンバーの中学生みたいなルックスとは裏腹に、充実した演奏に力強いボーカル、それに印象的な歌詞の世界に魅了された。
続いて『世界が終わる夜に』や『東京ハチミツオーケストラ』も強く印象に残り、そして『とび魚のバタフライ』の演奏を聴いて「ああ、あのときのグループか」とようやく気付いた。
幸運なことに高校の友達にチャットモンチーの好きなやつがいて、そいつにCDを何枚も借りて聴いた。そしてめったに行かないライブにも足を運ぶようになった。
バンドから高橋久美子が脱退し、チャットモンチーは二人体制になった。二人になってからも何回かライブに行ったが、自分の生活にも変化があって、いつしかライブへ足は向かなくなった。
それでもCDは買っていたし、過去の曲も繰り返し聴いていた。聴き続けるうちに好きな曲は変化して行った。最初は『親知らず』や『恋の煙』が好きだったが、気づけば『少年のジャンプ』と『コスモタウン』を延々と繰り返していて、そのうちに『ひとりだけ』や『Y氏の夕方』が最高だと思うようになった。
二人になって以降は『私が証』や『最後の果実』が好きだ。ただ、どうしても二人で作った曲よりも、過去の三人で作った曲を聴くことが多かった。
音楽のジャンルについてまったく詳しくないが、自分はチャットモンチーをロックバンドだと思っていた。特に橋本絵莉子のシャウト、あの可愛らしいのに力強い歌声を聴くたびに、チャットモンチーはロックバンド以外の何者でもないと勝手に確信していた。
あの歌声は二人になってからも健在だったが、なんとなく三人の頃の曲の方が聴き手をガツンと引き込むような力がある気がした。チャットモンチーは二人体制になってからバンドのスタイルを大胆に変更してきたが、そのせいか曲調もロック調のものよりもポップの方に寄った曲が多くなった。
チャットが変化していった理由として、三人の時と同じことをしても仕方がないという思いが二人にはあったのだろう。
また、メンバーも歳を重ね、人生が深まっていくにつれて過去の曲にこめられていた「切実さ」が薄れていったのではないだろうか。特に橋本絵莉子は結婚や出産という大きな出来事があり、その変化に合わせて徐々に、かつてのチャットモンチーが好んだ恋愛や思春期といったテーマが、瑞々しい曲の題材として機能しなくなったのではないか。二人になってからのチャットはもう一度切実に歌うことのできる新しい題材を得るために苦闘していたのではないか、と考える。
これは自分の考え足らずな空想かもしれない。自分よりもこのバンドのことを長く、深く追ってきた人は一笑に付すような意見かもしれないが、とにかく自分は二人体制のチャットの曲を深く聴き込んでなかったことをそういう風に解釈していた。
しかし、先日発売されたチャットモンチーの最後のアルバムを聴いた時、この解釈への自信がなくなってしまった。『誕生』と名付けられたこのラストアルバムに、自分はなぜこれほど感動するのだろう。高橋久美子が作詞した『砂鉄』のゆっくりとした、穏やかな全肯定には泣かされるし、さらにアルバムの最後を飾る『びろうど』のどうしようもない程の誕生への祝福がこちらの胸を打つ。
チャットモンチーは過去のスタイルにこだわらず、逞しく変化してきた。かなりの成功を手にしていたのに、バンドとして過去のスタイルにこだわらず、新しい道を模索し続けていた。そのことを自分は見くびっていたということだろうか。
数日後の武道館でのライブを、自分は映画館のライブビューイングで見るつもりでいる。チャットモンチーのライブを見るのは久しぶりだ。自分にとって本当に得難い経験を与えてくれたこのバンドが、どれほどの進化を遂げたか目に焼き付けるつもりである。
『黒の試走車(テストカー)』 増村保造
スポーツカーを巡る産業スパイたちの攻防を描いた、大映の『黒シリーズ』の第一作目である。
タイガー社に勤める産業スパイたち、リーダーの小野田(高橋悦史)とやり手の部下の朝比奈(田宮二郎)は開発中の新車・パイオニアの情報を守ろうとするが、業界最大手のヤマト社にデータを盗まれてしまう。ヤマト社では元関東軍情報部の馬渡(菅井一郎)が指揮をとり、スパイ活動を行なっていた。
馬渡へのリベンジに燃える小野田だが、恐喝や買収などあの手この手で対抗しようとしても、全て馬渡に上を行かれてしまう。どうやらタイガー社の中に内通者がいるらしい。
ヤマト社はパイオニアから盗んだ技術を元に新車を開発するつもりだ。このままではパイオニアの売れ行きは大打撃を受けてしまう。
朝比奈は恋人でバーの女給をしている昌子(叶順子)に、とあるバーに勤めてほしいと頼む。そのバーは馬渡の行きつけの場所だった。そこで馬渡から何か情報を聴き出すのが朝比奈の狙いだ。
「この件が終わったら君と結婚する」という朝比奈の言葉に折れ、昌子は渋々とバーで働き、馬渡に気に入られるのだが‥‥‥。
田宮二郎を始めとしたスマートで都会的な俳優たち、それに増村保造のテンポの良い演出と白黒の映像が「スパイたちの知能戦」という題材とマッチしている。
なかでも産業スパイのリーダー、高橋悦史が非常に目立つ。一人だけ黒のスーツに身を固め、会社のためというより惚れ込んだパイオニアのために命がけで働く男だ。
新車の情報を盗まれたことを「恋人を寝取られたようだ」とぼやくほどで、企業人としてこれ以上ない人間だが、企業のためなら家庭でも他人でも犠牲にしてなんら良心の痛まない、冷酷な人間でもある。
ヤマト社が開発する新車の情報を得るため、高橋たちは相手企業の幹部を工事現場で脅す。暴行され、地面に這いつくばった幹部を高橋を含めた三人の男たちが見下す姿は、ギャングの姿そのままである。
こういった産業スパイの姿には戦中の特高警察など、強権的な組織の姿が投影されているのかもしれない。敵が元関東軍の情報将校だったり、「警察や軍隊と一緒だ」というセリフがあったり、公開当時は戦争が遠いものではなかったことがわかる。
ハイライトは船越英二と高橋悦史、密室での二人の攻防だろう。高橋の仕掛けたトラップがわかりやすすぎるのが難点だが、高橋の熱量、船越の焦燥の演技で緊張感が保たれ、目が離せない。
船越が厳しく追求してくる高橋を「警察のつもりか」となじる。対して高橋は「おれは産業スパイだ」と誇らしげに言う。このシーンの禍々しさはなんだろう。会社の為といった大義名分から外れ、己の執念にとりつかれた男の狂気。そういったものさえ感じられる。
組織の持つ暗黒を、高橋が一身に表現している。そんな高橋が、最後に自分の元を去る田宮を呼び止めようとするのがちょっと切ない。田宮を自分の家に連れて行ったり、本気で後継者にするつもりだったのか。
もう一人、忘れてはならないのが上田吉二郎だ。ヤマト社の情報をリークする業界新聞の記者役で、階段を登るたびにヒーヒー息切れする、ぶくぶく太った男。そんな上田が終盤、暗闇の中から突如現れるシーンの悪漢っぷりが素晴らしく、もはやかっこよく見えてくるほどだ。
強い印象を残す男たちの中で、肝心の田宮二郎はいつもの色男っぷりが影を潜め、妙に理屈っぽく、世間知らずの男に見える。「僕は人間らしく生きたい」と高橋悦郎を非難するセリフも妙に青臭い。
田宮が自分の恋人を利用しながら「結婚しよう」と言い続けたり、敵のスパイの親玉に恋人の体を与えながら後悔するシーンなどは無邪気ささえ感じられる。
いまいち貧弱な田宮に対し、本作に出てくる女性たちは非常にたくましい。理屈に囚われず、目的のために平気で相手を出し抜いて生き抜こうとしている、そういう女性のたくましさに増村保造の個性を感じる。
とくに強烈なのが病室を盗聴していた看護婦で、自分が裏切った船越を「往生際が悪いわよ」とぴしゃりと斬って捨てる、その欲ぶかさと冷酷さにはピカレスクな魅力がある。
だが、最も魅力的なのは田宮の恋人役・叶順子だ。田宮に「結婚しよう」と言われても、笑って真に受けない。若くして人生の酸いも甘いも噛み分けたような、アンニュイな雰囲気の女だ。豊満な肉体に挑発的な瞳が強い存在感を放っていて、惚れた男に従う単純な女ではなく、自我を持った人間として描かれている。
都会的な色男・田宮二郎が本来の魅力を発揮できていない時、この叶順子のアダルトな雰囲気がバランスをとって、映画を引き締まったものにしている。
最後、叶順子はこれまでの出来事を受け入れて田宮と共に生きていく。「やっぱり愛が大事」という結末が甘く、だらしないものになっていないのは、この叶順子の存在があったからだろう。
『リズと青い鳥』山田尚子
「響け!ユーフォニアム」のテレビ版も映画版も未見である。吹奏楽部や京都アニメーションにもそれほど興味はないが、友人にこの映画を勧められて鑑賞してきた。十分におもしろかった。そして予想以上に百合だった。
本作は全体を通して、「静かな映画」いう印象が強い。演奏シーンを除いて派手な音楽は使用されず、心理描写にもあまり過剰な演出は見られない。
その代わりに力を入れているのが音や人物の動きの演出で、特に印象的なのが序盤でみぞれと望美が待ち合わせし、音楽室へ歩いて行くシーン。セリフもほとんどないが、みぞれの足や視線の動き、望美の跳ねる髪やターン、そういった写実的な映像が魅力的で、見飽きるということがない。
また、些細な生活音にもこだわっている。上履きと床の擦れる音、絵本のページがたわむ音などが臨場感を高めている。
ストーリー自体も控えめで、劇中で大きなイベントはほとんど起こらない。舞台はずっと学校の中だし、主人公たちがプールや祭りに行くサービスシーンもばっさりカットされている。
学校へ行き、授業を受け、吹奏楽部に通う。そういった当たり前の日常を通して描かれるのはみぞれと望美、ふたりの女の子の物語である。このふたりの関係が童話の『リズと青い鳥』になぞらえて変化して行く。その過程を映画は丁寧に掘り下げる。
明るく友達も多い望美と、望美に依存気味で無口なみぞれ。ふたりの関係は予想以上に百合百合している。特に望美が向かいの校舎にいるみぞれを見つけ、フルートに反射し多光がみぞれまで届く場面。このシーンに漂う空気感というか、雰囲気は筆舌に尽くしがたい。
本作は静かな映画だが、見終わった後にかなりの充実感がある。
それは「大切なものが終わる」瞬間が、劇中で鮮烈に描かれているからだろう。
そのひとつが終盤の演奏シーンだ。この演奏シーンもコンクールの大舞台などではなく、音楽室で大会に向けての練習という、視覚的に地味な場面だ。しかし、決して見劣りしない。
覚醒し、完璧な演奏を見せるみぞれと、みぞれの才能に気づいてしまった望美。キャラの感情の変化と音楽の盛り上がりがシンクロし、すごく見応えのあるシーンになっている。
そして終盤の理科室のシーンだ。ここはこの映画のハイライトだろう。みぞれは秘めていた感情を全てむき出しにして、ぶつかっていくが、望美は痛恨の決断を下す。
こういった場面でも、作り手はキャラを派手に泣かせたり、心情を叫ばせて表現したりはしない。ただ、キャラの細かい動きや呼吸音など、小さなディティールを積み重ねる。
そういった細部のクオリティと、役者の演技を中心に構成することで、むしろシーンは力強いものになっている。
ここでみぞれ役の種﨑 敦美、望美役の東山奈央 、二人の役者が最高の演技を見せる。
「みぞれのオーボエが好き」と言った時、望美は何を思っていたのか。「自分とは別の道を歩いてほしい」と伝えたかったのか。それとも「望美のフルートが好き」と言って欲しかったのか。
今までとは違う世界を生きなければならない望美が、ひとりで廊下を歩いて行く。このシーンはかなり切ない。
望美は「ハッピーエンドがいい」と何度か口にするが、この終わりはハッピーエンドなのか。本作では明確に描かれていない気がする。作り手はわかりやすい救いや愁嘆場を用意していない。
ただ、主人公たちは前とは少し変わった日常を生きる。高校生の彼女たちにとって、今はまだ道半ばなのだろう。このあとも人生は続く。そうやって日常を続けるうちに、彼女たちの決断がハッピーエンドなのか、初めてわかるのかもしれない。
ラストシーンで望美は「みぞれの演奏を支える」と言う。この言葉には決意が詰まっている。大事なものが終わってしまっても望美は立ち止まらない。また新しい関係を築いていこうとする。立ち止まらずに歩いて行くその先に、ふたりにとっての幸福があればいいと思うのだ。
ちなみに、ネット上のいろんな人の感想文によると、見ている人によってみぞれと望美、どちらに感情移入するか分かれるようだ。自分は途中から完全に望美に感情移入していた。
そのためか、終盤から頭のなかで「技術的な理由で聖飢魔Ⅱを脱退したゾッド星島親分」のことがぐるぐる回って仕方がなかった‥‥‥という信者にしかわからない話で感想文を終える。

- アーティスト: 聖飢魔II
- 出版社/メーカー: ソニー・ミュージックレコーズ
- 発売日: 1988/06/22
- メディア: CD
- 購入: 1人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
一つの写真、一人の男 『キャパの十字架』沢木耕太郎
ロバート・キャパ。スペイン内戦を始め五つの戦場を駆け回り、最後は地雷によってこの世を去った伝説の戦場カメラマン。特にスペイン内戦で撮ったある写真は、のちの報道写真のあり方を決定づけたと言われるほど重要なものとなった。
その写真は『崩れ落ちる兵士』と呼ばれた。頭を撃たれた兵士が文字通り崩れ落ちる瞬間をとらえた傑作だが、この写真には多くの謎が残っている。
スペインのどこで、いつ撮られたのか。本当に撃たれた兵士を撮った物なのか。キャパがこの劇的な瞬間を撮影できたのはなぜか。
やがて兵士は撃たれたのではなく、倒れた演技をしているだけだという「やらせ疑惑」も出て、未だ議論は絶えない。
そんなキャパと『崩れ落ちる兵士』について、沢木耕太郎は前から並々ならぬ興味を持っていたようだ。それがわかるのが『キャパの十字架』に先立つ二十年以上前に書かれた「三枚の写真」という文章である。これは『象が空をⅡ 不思議の果実』に収録されたものだが、この文章を書いている時、沢木はキャパの評伝を翻訳している最中だった。
この文章ではすでにキャパと「崩れ落ちる兵士」の真贋について言及しているし、さらには「大きな十字架を背負ったキャパ」という『キャパの十字架』とほぼ重なる表現も出てくる。他にもいろいろな文章で沢木のキャパについての言及は見られ、沢木にとってキャパという存在がどれだけ大きかったかがわかる。
そして沢木は、ついに『崩れ落ちる兵士』の真贋についての調査に乗り出した。スペインを何度も訪れ、関係者へのインタビューを重ね、その結論が本書『キャパの十字架』である。
最初に不満点を挙げておく。本書にはキャパやゲルダが撮ったいくつもの写真が縮小されて掲載されているが、目の悪い自分には写真の細部が見えにくくて困ってしまった。自分は文庫版を読んだので、単行本よりも余計に写真が小さくなっていたのかもしれない。
沢木の検証では隅っこに写っている小さな草や雲が重要な意味を持ってくるのだが、小さい写真を見比べるのに疲れ、せっかくの検証を十分に楽しむことができなかった。
それでも本書はおもしろい。特に印象に残るのは写真の持つ脆弱性と、キャパという人物の持つ魅力である。
本書を読んで、写真というものの脆さに改めて気付かされた。
トリミングやキャプチャーなどの編集によって写真の印象は大きく変わる。さらには写真を紹介する者の意思によって、写真は平気で嘘をついてしまう。
例えばススペレギ教授と曾祖母の写真のエピソードがある。このスペイン人の教授はキャパの写真がフェイクであることを指摘し、沢木の検証に大きな影響を与えた人物である。
そのススペレギ教授の曾祖母はスペイン内戦中、フランスへ逃げようとする民衆の一人だった。逃げる途中、海岸に座り込んだ曾祖母の姿を、ある報道カメラマンが写真に残していた。この写真はトリミングされ、様々な雑誌に掲載される。
編集されていくうちに、写真はどこで撮られたものか、被写体の女性は誰かが曖昧になっていく。そのうちに、写真は全く関係のないゲルニカの空爆の被害者を写したものとして扱われてしまう。
写真の「事実」を歪めるのは簡単なことなのだ。こういった写真の脆さは『崩れ落ちる兵士』も例外ではない。
ただ、その一方で写真が予想以上に多くのものを語ることも事実なのだ。一瞬を切り取った写真をくまなく精査するとき、写真は思いもしなかった事実の一片を見せてくれる。
沢木の検証は写真の隅に映る小さな断片を調べることで始まる。そういったごく微小な細部を積み重ねていくことが予想以上の仮説を生み出し、事実への接近を可能にする。
そうした事実と仮説の積み重ねの末、いろいろなことが明らかになっていく。キャパはどのように撮影を行ったかということも、最初は重要視されていなかったキャパの恋人、ゲルダ・タローが『崩れ落ちる兵士』に深く関わっているかもしれないことも。そしてロバート・キャパという人間についても。
沢木は細かい検証を重ねながら、キャパという人間をもう一度捉え直そうとする。何度もスペインに行き、撮影場所を探しに歩き回り、写真の隅の隅を見比べる。そうした作業を繰り返す内、キャパが背負った「罪」の存在と、「十字架」を背負いながら幾多の戦場を渡り歩いた男の姿が徐々に露わになっていく。
そのとき、読者の前には非凡な力を持ち、戦場を嫌いながら戦場を必要とする男の、物悲しい姿が存在感を持って浮かび上がってくるのだ。
本書は単にキャパの神話を剥ぐだけのものではない。沢木があれだけの時間と手間をかけて謎を追ったのはキャパを否定するためではなく、キャパの新たな実像を描くためだった。そういう印象を受ける。
キャパの行為を糾弾することもできただろう。ただ、沢木はそうしなかった。
そうして本書を振り返ったとき、読者に残るのは、あとがきで作者が振り返ったとおり「旅をした」という余韻である。
写真の謎を追いかけることが、キャパの足跡を巡る一つの旅となる。その旅が終わったときに残る読後感が、本書の最大の魅力かもしれない。
『スーパーカブ』 トネ・コーケン
自分はバイクに乗ったこともないし、カブに触ったことさえない。これから乗ることもないだろう。
そんなバイクへの興味がペラペラにうすい人間でも、この『スーパーカブ』は楽しく読むことができた。
<ストーリー>
山梨の高校に通う女の子、子熊。両親も友達も趣味もない、何もない日々を送る彼女は、中古のスーパーカブを手にいれる。初めてのバイク通学、ガス欠、寄り道、それだけのことでちょっと冒険をした気分。仄かな変化に満足する子熊だが、同級生の礼子に話しかけられ——「私もバイクで通学してるんだ。見る?」一台のスーパーカブが彼女の世界を小さく輝かせる。ひとりぼっちの女の子と世界で最も優れたバイクが紡ぐ、日常と友情。
(裏表紙より引用)
続きを読む今日ですべてが報われる『15時17分、パリ行き』 クリント・イーストウッド
今の流行りは寿司ですよ 『希望のかなた』アキ・カウリスマキ
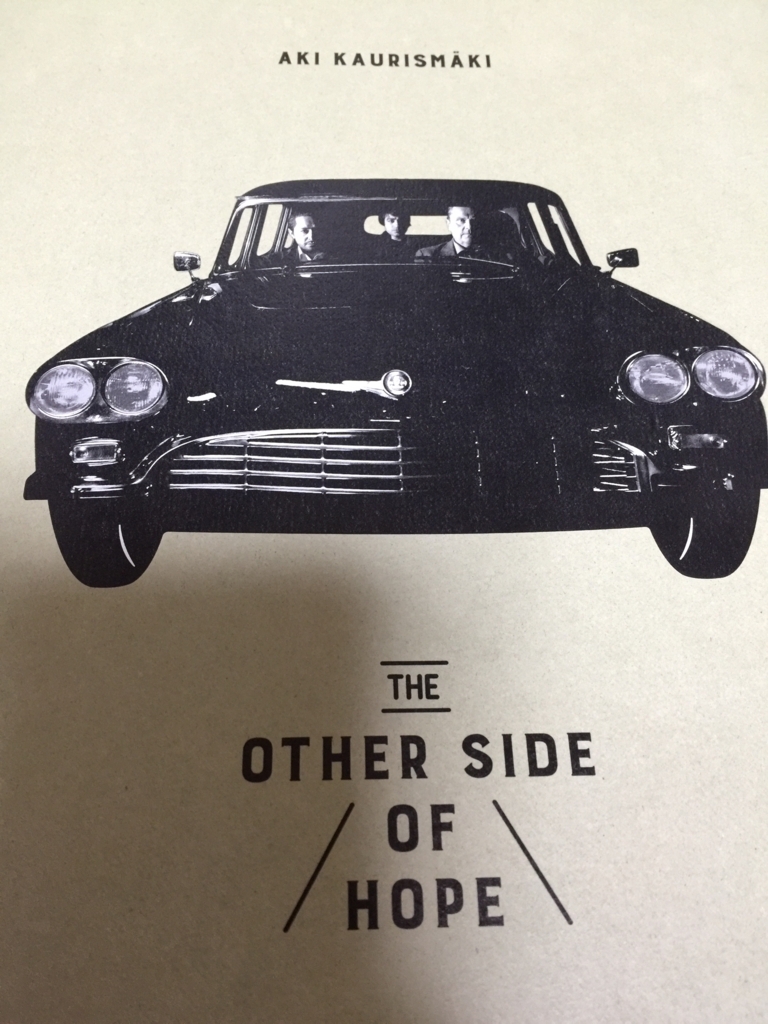
アキ・カウリスマキの最新作であり、前作『ル・アーブルの靴磨き』から続く「難民三部作」(元は「港町三部作」と呼ばれていたが、いきなり変更された)の二作目である。
今作でもカウリスマキのトレードマーク(犬、音楽で心情を表現する演出、シンプルなカメラワーク、あざやかな色彩、極端に少ないセリフ、個性的な顔の俳優たち)は健在である。しかし、いつも通りのカウリスマキのようで、新しい部分もある。
それはシリアからフィンランドに密航したシュルワン・ハジが亡命を求め、移民申請のための取り調べを受けるシーン。取調官の前で、ハジは移民となった経緯を淡々と話す。政府軍の空爆で家族が殺され、唯一生き残った妹と命がけの逃亡、その妹ともはぐれ、最後の希望がフィンランドへの亡命であること。自分の望みは妹を探し出し、フィンランドに呼び寄せること。ただそれだけだと。
家族を殺されたことを、ハジは必要以上の感情を交えず、淡々と話す。その顔をアップでカウリスマキは撮り続ける。寡黙を良しとするカウリスマキの映画で、ハジは長いセリフで自分たちの危機と、難民の現実について語り続ける。
カウリスマキのミニマムな世界観において、このシーンには異質なものを感じる。このシーンには難民について作り手からの強いメッセージがある。
カウリスマキは本作について、難民についてのヨーロッパの偏見を打ち砕く「傾向映画」として作ったと語っている。そのためにいつもの寡黙さを捨てて、俳優の雄弁な語りによってリアルな難民の姿を表現しようとしている。
こういった志が、本作に「いつものカウリスマキ映画」以上の新鮮さを与えている。
また、本作の主人公、サカリ・クオスマネンも今までのカウリスマキの主人公たちとは一味違う。
酒浸りの妻と別れ、服の卸売からレストランのオーナーへの転職を夢見る無口な中年男。ここまではいつものカウリスマキの主人公だが、クオスマネンはレストランの開店資金を稼ぐために怪しげな賭場に乗り込み、大勝負を挑むのだ。
今までのカウリスマキ作品の主人公たちを思い出してほしい。マッティ・ペロンパーやマルック・ペルトラがこういうときに勝てたことがあっただろうか。カウリスマキの主人公たちはいつも敗者だ。特に金の絡んだ勝負には勝てない。ずる賢い奴らに金をむしりとられる、それが今までの主人公のパターンだったはずだ。
ところが今作のクオスマネンはしたたかに、順調に勝ち進み、なんとギャングの親玉から大金を巻き上げ、悠々と脱出することに成功してしまう。これにはおどろかされた。かつてカウリスマキの映画で、こんな大勝利があっただろうか?
立派な体躯にふてぶてしい顔のクオスマネン妙に頼もしい。このクオスマネンが購入したレストランの敷地に、移民収容所から逃げ出してきたハジが隠れ住む。
追い払おうとするクオスマネンにカッとなり、ハジはパンチを見舞う。すかさずクオスマネンが殴り返す。次のシーンではレストランでハジに食事がふるまわれている。
オーナーの「ここで働くか?」の提案に、ハジは力強く応える。こうしてハジはレストランの従業員として働くことになる。
フィンランドに逃げ延びたハジの前には、移民申請を機械的に否決し、強制送還を命令する冷徹な裁判所や、ネオナチかぶれの男たちによる暴力などが立ちふさがる。こういったヨーロッパの冷たい不寛容にどう立ち向かえば良いのだろう。カウリスマキの出した答えは人々の小さな親切の大切さである。
暴力にさらされながらも、ハジの周りはささやかな親切で満ちている。フィンランドへ向かう船の船員、収容所で出会う人たち、ホームレス、レストランのメンバー、そして「礼はいらん。素晴らしいものを運ばせてもらった」と言って謝礼を受け取ろうとしないトラック運転手。これらの人々の純粋な善意がハジへの救いとなる。
今作は難民をめぐる厳しい現実を描きながら、要所でユーモアがちりばめられ、映画の雰囲気をやわらかいものにしている。
自分が好きなのはレストランで働き始めたハジの期限切れビザをどうするか?というシーン。その解決方法があまりに都合が良すぎて、真面目なのかギャグシーンなのかよくわからない。
しかし、本作の笑いどころは満場一致で「寿司レストラン」のシーンだろう。これに至ってはいつもの「オフビートなユーモア」というより、もはやナンセンスギャグである。
売上の芳しくないレストランをどうしようと皆が頭を悩ませる中、「今の流行りは寿司だ」とウェイターのテキトーな提案で、レストランは一気に日本風につくりかえられる。
提灯で飾られた店内にドラが鳴り響き、法被とハチマキと前掛け(日本語で「最高級品 大勉強の店」と書かれているのがまたおかしい)を着けた店員が日本酒を運び、厨房では難しい顔をしたコックが寿司を握っている。シャリに刺身をのせ、さらにでかいスプーン一杯分のわさびをドンとのせた寿司のヴィジュアルはあまりに強烈だ。
デタラメな日本のイメージに頭がクラクラしてくる。これまでシリアスなシーンが多かった反動か、カウリスマキもここでは大いにボケ倒す。
だが、自分がもっともショックだったのはその前のシーン。寿司のつくり方を学ぶため、本屋で寿司の本を片っ端から購入する場面である。
クオスマネンは日本語で書かれた本を大人買いするが、なんとその中に池波正太郎の『真田太平記』と藤沢周平の『孤剣』の文庫本が含まれているではないか!
まさかフィンランドの、カウリスマキの映画でこの二冊が登場するとは思いもしなかった。カウリスマキはどこでこれらの本を知ったのか?もしや読んだことがあるのか?
こんな日本人にしか通じないギャグをさらっと入れてくることに、唖然とするやらおかしいやら、とにかくインパクトの強いシーンだった。
前作『ル・アーヴルの靴磨き』を、カウリスマキはあまりに都合の良いハッピーエンドで締めくくり、そして観客はそれを大いに祝福した。しかし今作のラストでは苦い結末が待っていた。
ハジは離れ離れになっていた妹を助けることに成功するが、非情な運命を辿ってしまう。現在のヨーロッパを取り巻く状況では、『ル・アーブル-』のようなハッピーエンドはそぐわないものになってしまったのかもしれない。
それでも、不思議と後味が悪くないのは、全てをやりきって座り込んだハジのもとに、寄り添ってくる一匹の犬のせいだろうか。
映画の終わりかたは唐突なように感じたが、あの後を映さないことがカウリスマキの優しさなのだろうか。その後、ハジがどうなったかを観客の自由な想像に任せられるように、見た人の頭の中で、ハジが幸福な結末を迎えられるように、あえてカウリスマキはあそこで幕を下ろしたのかもしれない。
順調につくられるなら、難民三部作は次が最終作となる。激しく移り行く世界の中で、次作はどのような結末を迎えるのか。
不安なのは今作の序盤で、カウリスマキ映画の象徴、カティ・オウティネンがフィンランドを去り、メキシコへと旅立ってしまったことである。
このカティ・オウティネンの不在がどこか不吉なものに感じられてならない。オウティネンが見切りをつけるほど、今のフィンランドは生きづらい場所なのかもしれない。
何年後かに最終作がつくられるとき、世界はどうなっているのだろうか。たとえ現実の世界がどれほど冷たく非情なものになっていたとしても、どうか『浮き雲』のときのような、幸福な結末でシリーズを締めくくってほしいのだが。
もっとも、シリーズ名がまた突然変わっているのかもしれないが‥‥‥。

![黒の試走車 [DVD] 黒の試走車 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51TkWbLnf3L._SL160_.jpg)




